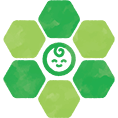掲載日:2025年1月30日
日本交通株式会社
育業の情報が社員同士の“口コミ”で広まる。
子育て世代社員の増加に合わせて、働きやすさ向上に取り組み続けるタクシー会社。
日本交通株式会社は、「桜にN」のマークで多くの人に親しまれる、タクシー業界の老舗企業です。グループ全体で18,000人以上の従業員が働く同社では、働きやすさの向上のためどのような取組を行っているのでしょうか。
同社 人事労務部部長の鷲 幸男(わし さちお)さんと、2023年に育業した人事労務部の安城 友裕(あじろ ともひろ)さんにお話を伺いました。

タクシー業界特有の勤務体系が育業日数増加を後押し
―御社の男性育業の状況を教えてください。
人事労務部長 鷲幸男さん(以下、鷲):弊社男性社員で今年育業した人数は約50人、育業取得率は71.4%。平均日数は174.3日でした。

―平均日数が174日というのは長いですね。
鷲:弊社は社員の8割が乗務員、いわゆるタクシー運転手です。乗務員の勤務は一人休んでも誰かが業務を引き継ぐような体制ではありませんので、他業種と比べると長期間育業しやすい環境と言えるかもしれません。
乗務員以外の社員も、2022年に施行された「産後パパ育休(出生時育児休業)」などの制度を利用しながら、2~3ヶ月間育業する社員もいます。
人事労務部 安城友裕さん(以下、安城):私自身も2023年に2ヶ月間育業しましたが、身近な先輩が1ヶ月育業していたこともあり私も積極的に制度を活用したいと思っていました。
―男性の育業推進に注力しはじめたきっかけを教えてください。
鷲:数年前に始まった公益財団法人東京しごと財団の「働くパパママ育業応援奨励金 ※」の存在が大きかったと感じています。会社ごとに支援を受けられる制度なのですが、弊社は営業所一つひとつが個別の会社となっているため営業所の所長たちの間で制度の存在が広まり、多くの営業所が活用しました。この奨励金のおかげで会社・営業所側の負担も軽減でき、育業する社員を送り出す環境の整備が大きく進んだと思います。
また、2012年から人材投資として乗務員の新卒採用にも注力していて、現在までに1,900名以上の新卒社員が入社しています。その結果、社内の子育て世代のボリュームが年々増加しており、そうした社員の労働環境整備という意味でも、育業推進に取り組みやすい社内環境だと言えるかと思います。
※公益財団法人東京しごと財団「働くパパママ育業応援奨励金」
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/papamamaikukyusyutoku.html
安城:私も2019年に新卒で入社した社員の一人ですが、横のつながりの強さが若手の特徴のひとつだと思います。同期入社であれば自主的にLINEグループなどでつながっているため、乗務員として異なる営業所に配属されたあともよく連絡を取り合っています。
そのため、誰かが一人育業すると口コミで多くの同期に広まり、「自分も子供ができたら育業しよう」と思いやすい環境なのではないかと思っています。
鷲:新卒社員では個人間のグループだけでなく会社が公式LINEのようなアカウントも運営していて、社内制度など様々な情報を発信しています。育業に関する情報もそちらでアナウンスを行っていますので、社員にとって育業がより身近な制度になっているのではないかと考えています。

―育業を推進する中で課題となった点はありましたか?
鷲:「育業することで人事考課に影響するのではないか」と懸念する社員がいる可能性は否定できません。
もちろん育業によって不利になるような評価はしていませんが、評価される側としては気にしてしまう部分はあるかもしれません。そうした懸念をなくすためにも、育業制度の周知は欠かせないものだと思っています。
一方で、弊社は社員の多くが乗務員で出勤のタイミングがバラバラのため、対象者が一堂に会して研修会を受けることが難しい環境でもあります。そのため先にお伝えしていたLINEを使った情報共有や、乗務員から運行管理者になる社員が受ける労務研修などで繰り返し発信し、育業を中心とした様々な制度の認知を高めていきたいです。
チームの協力のおかげで、不安なく取り組めた育業体験
―先ほど安城さんは2023年に2ヶ月間の育業を経験されたと仰っていました。
安城:はい。以前から育業に関する制度があることは知っていたのですが当時は「そういう制度があるらしい」程度の認識で、しっかり調べるようになったのは子供が産まれるとわかってからでした。
上長や育業した先輩などに教わりながら自分でも社内規定で利用できる制度を確認して、調べていく中で出産祝い金などの社内制度も存在することを知り利用しました。

―社内での育業の準備はいつ頃から始めたのでしょうか?
安城:妻が安定期に入った頃から徐々に進めていきました。私の所属は新卒採用部署ですので、当時も担当する学生を抱えていました。その学生たちにも「2ヶ月育業するけど、その間は別の担当がつくから安心してね」とお伝えしていました。
担当を引き継ぐ同僚たちも育業に対して理解し協力してくれていたので、仕事に対する不安は何もありませんでした。心配していたのは仕事のことよりも「子供ってどうやって育てたらいいのかな」など育児のことばかりでしたね。
―育業中のエピソードを教えてください。
安城:2時間おきに子供にミルクをあげたりおむつを交換したり、毎日お風呂に入れてあげたりしていました。私一人で子供の世話をするわけでなく、妻も協力してくれてどちらか一方に負担が集中しないような状況だったので、私自身はあまり負担を感じることはありませんでした。
復職後の話になるのですが、子供が1歳になる頃、ほぼ1週間おきに風邪を引いていた時期があって、保育園に預けて出勤したあと1時間程度で「熱が出ました」と保育園から連絡を受けて迎えに帰ったこともありました。そのときは安定して仕事ができないということで、上司やチームに相談してリモートワークで働けるようにしてもらいました。まわりの配慮もあったことで、復職後も育児と仕事の両立がしやすかったと感じています。
―育業の経験が仕事に活用できている点はありますか?
安城:将来的に育業したいと考える男子学生が「育業した人の話を聞きたい」と希望してくれて、育業の経験者として面談する場をセッティングしてもらうことはありますね。今の学生世代は男性も育業への関心が高いのだなと感じます。
また、これは仕事の分類にはならないかもしれませんが、私が社内の育業経験者からアドバイスを受けたのと同じように、自分でも後輩に対して育業を勧めることを心がけています。私からアドバイスを受けた後輩が次の後輩に育業をアドバイスする。今後もさらに受け継がれていくことで、もっと社内で育業が当たり前になってほしいです。
社内と社会全体の育業を後押ししていく

―育業から復職された方々はどのような働き方をしていますか?
鷲:当人の所属する部署によって対応できる範囲は異なるのですが、先ほどお話しした安城のように家庭の事情に合わせて自宅からリモートワークで働いた例もあります。
また、スタートして間もない取組ですが、社内の女性活躍推進を目指す「さくら小町プロジェクト」の中で復職した女性社員の働きやすさの改善も進めています。乗務員の勤務体系は“1日働いて1日休む”「隔日勤務」が主体で、育児中の女性はこの働き方が難しいケースもあります。そのためどんなシフトであれば育児中の女性が働きやすいのか、2023年から検討を進めています。
―今後、さらに育業を推進していく中で目標はありますか?
鷲:育業が当たり前の会社になることがひとつの目標です。社員一人ひとりが自身のニーズに適したかたちで育業できるように社内体制を整えながら、制度の認知を広げていきたいと考えています。
記事の内容は掲載時点の情報に基づいております。
紹介した企業・団体
-

日本交通株式会社
- 住所
- 東京都 千代田区紀尾井町 3-12
-