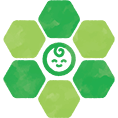掲載日:2025年3月26日
日本ハム株式会社
働きがいのある柔軟な企業を目指して。
引継ぎ方法の見直しで、業務の属人化解消にもつながった育業推進
日本ハム株式会社は、食肉をはじめ加工食品から水産加工品、乳製品など食に関するあらゆる分野で、“食べる喜び”を消費者に届け続けている企業です。同社では多様な人財の活躍に向けて、DE&Iにつながる働き方改革に取り組んでいるといい、男性の育業推進も取組のひとつに位置付けています。
今回は、同社人事部リーダーの臼井 佐知子さんと食肉事業本部 管理統括部 事業企画室の篠崎 優大さんにお話を伺い、取組の内容やその目的について伺いました。
社内制度の導入で長期の育業が増加
―御社の男性育業の状況を教えてください。
人事部リーダー 臼井佐知子さん(以下、臼井):当社では2019年に「育児と仕事ガイドブック」を作成するなど以前から育業に注力していました。そうした中、2022年の「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度のスタートもあり、育業する社員は年々増加傾向にありました。
そうした環境の変化を受けて2023年度からは、子供が産まれた際に利用できる有給休暇扱いの「特別休暇」制度を導入し、連続した5日間の制度利用を義務化しました。その結果、現在は男性も全員が育業しており、育業した日数は平均で21.6日(2023年度実績)となっています。
―新たな制度の導入によってどのような変化があったのでしょうか?
臼井:これまでよりも長く育業する社員が増えてきたと感じています。特別休暇制度は最大で20日利用できるため、公的な制度と合わせて1ヶ月間以上の育業がしやすくなりました。
食肉事業本部管理統括部事業企画室 篠崎優大さん(以下、篠崎):私も2023年度に約3ヶ月間育業しましたが、私が復職してすぐ同じ部署の同僚が約2ヶ月間育業しました。彼が復職したあと「先に育業していたのを見て、自分もしっかり育業しようと思えた」と言っていたので、私が育業したことで推進に貢献できていたら嬉しいです。
臼井:篠崎の言うように、制度として長期の育業がしやすくなったことで長期育業する社員が増え、それを見た他の社員が自身も長期での育業を検討するようになる。育業の意識が浸透し、そんな相乗効果が生まれているのだと思います。事実、導入した2023年度は特別休暇制度の利用は平均で10日前後でしたが、まだ期中ではあるものの2024年度には平均16日にまで伸びています。
―育業をさらに推進していくうえで感じている課題はありますか?
臼井:復職後の社員にアンケートを取ってみると、「もっと長く育業してもよかった」という意見がありました。実際に、当初は3ヶ月間の予定だった社員が、育業中に10ヶ月間に変更したケースもありました。
篠崎:「もっと長くてもよかった」と思う気持ちは分かる気がします。私の場合は3ヶ月間でしたが、子供がある程度大きくなって生活リズムが安定していたとはいえ、振り返ってみればまだデリケートな段階だったと思います。後から思えば、ワンオペでもある程度安心して育児ができる半年くらいまでは育業してもよかったかなとも思っています。
臼井:育業が当たり前になってきている実感はありますので、さらに推進していくには長期の育業の際に業務を引き継ぎやすい人員配置を検討するなど、社内でもより育業しやすい体制を作っていく必要があると感じています。
育業を経験して、一人での育児にも自信を持てた。

―育業したときのことを教えてください。
篠崎:私の場合は2023年の10月下旬から93日間、約3ヶ月間育業しました。産まれた翌日の午後から育業に入ったので、妻と子供が入院している間は役所に行って手続きをしたり、買い出しで育児用品を準備したりしていました。
退院の前日には「パパも泊まれます」ということで私も病院に泊まって、妻と一緒にミルクの作り方やおむつの替え方など育児のノウハウを看護師さんに習いました。そこで具体的に実践することができたので、家に帰って自分でやるときも過度に不安にならずに済んだかなと思います。
―育業中はどんなことを担当されていましたか?
篠崎:できることは全部やっていました。病院で「出産した女性はかなり体力を消耗している」と教わっていたので、とくに最初の1ヶ月間は子供の世話や家事など先回りして動くことをすごく意識していました。私と妻で交互にミルクを担当していましたが、3時間おきにミルクを作って飲ませるのはやっぱり大変でしたね。飲んだあと子供がすぐに寝てくれたらいいのですが、毎回そうとも限らないですし、泣き止まないこともあります。1ヶ月くらいしてようやく落ち着いて寝かせるコツがわかってきました。
他にも、復職する1週間くらい前に妻が高熱を出してしまって、3日間ほど子供の世話と妻の看病を一人で行うこともありました。その頃には約3ヶ月分の育児経験があったので困るようなことはなかったですが、自分が妻の手を借りずに子供の世話ができていることを再認識して、育業してよかったと実感しました。
育業推進で業務の属人化が減少
―今後の育業推進の展望について教えてください。
臼井:今後は育業する日数を増やしていきたいです。目標は2026年度までに平均45日としています。
―目標到達のためにどのような取組を行っていく必要があるのでしょうか?
臼井:社内での育業事例を紹介したり、業務を引き継ぎやすくしたりすることで、長期の育業を増やしていけないかと現在検討中です。事例紹介は2024年にも実施していて、社内で育業した男性社員を対象に育業中にしたことや育業したことで変化があったかヒアリングを行い社内報に掲載しました。同じニッポンハムグループで働く社員同士でも、普段は他部署や他拠点の社員が育業していることを知る機会はあまり多くありません。社内報で紹介することで「うちの会社は育業している人がこんなにいるんだ」と知ってもらったり、自部署と似た業務を行う部署での長期育業をモデルケースにしてもらえたらと思っています。
業務の引継ぎは先ほどお伝えした部分と重複しますが、人員配置の見直しで引き継げるメンバーを増やしたり、業務の棚卸しを行い、引継ぎ作業自体を容易にできたらと考えています。
篠崎:私が育業の際に所属していた部署でも、今後の育業増加を見据えて業務を引き継ぎやすくするため日常的な業務がローテーションで行われるようになりました。それまでは担当者がほぼ固定され、本人しか把握していないノウハウが多数ありましたが、ローテーション化することでメンバー内でノウハウが共有され、業務の属人化が解消できるようになったと思います。業務の属人化が減ることで育業しやすくなりますし、復職後にも子供の発熱などの突発的な出来事も周囲がカバーしやすくなるのではないかと思います。
臼井:属人化が解消されたり、他者の視点が入ることで一人では気づかなかった視点から作業を洗い出して業務を効率化したり。育業をきっかけとした業務の棚卸しによって、生産性の向上も果たせると思います。さらに業務効率化・生産性向上は労働時間の削減につながり、社員全体のライフ・ワーク・バランスの向上にもつながります。
一人ひとりの価値観に合った柔軟な働き方を可能にすることで働きがいのある職場を実現し、社員全員のエンゲージメントを向上させることにも期待したいです。
記事の内容は掲載時点の情報に基づいております。