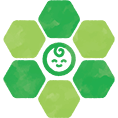掲載日:2025年3月28日
株式会社エブリー
子育ては、ともに手をとりあい行うもの
育児情報をシェアするアプリで育業を後押し
株式会社エブリーは、レシピ動画サービス「デリッシュキッチン」や「トモニテ」、「TIMELINE」など、生活者に寄り添うサービスを展開する企業。サービスを通じて企業ミッションの「前向きなきっかけを、ひとりひとりの日常にとどける。」に取り組んでいます。
今回は、同社執行役員でトモニテカンパニー長を務める三ツ中 菜津美(みつなか なつみ)さんに、同社がどのように男性の育業推進に取り組んでいきたいと考えているのかについてお話を伺いました。
ママだけじゃない、家族みんなの子育てを応援
―御社の男性育業の状況を教えてください。
トモニテカンパニー長・三ツ中菜津美さん(以下、三ツ中):当社では毎年10名弱の男性社員が育業しています。2019年頃から育業する男性社員が増えていき、2024年の育業取得率は100%となりました。
―男性の育業がスムーズに社内に浸透していったのは理由があるのでしょうか?
三ツ中: 当社の事業の性質上、育業などの取組に関心を持つメンバーが社内に多いのだと思います。私がカンパニー長を務める「トモニテ」も、「子育てを通じて、人が、社会が、ともに手をとりあう世界を実現する。」をミッションに位置づけてSNS・WEBメディアや育児アプリを運営しています。育児に関連するサービスを提供する側として社員の育業を含む育児に対する積極的・前向きな意識が醸成されてきているのかもしれません。
また、社会のニーズを的確に捉えてサービスを提供していく必要がありますので、社員自身も変化に対する感度が高くなっているのだろうと思います。トモニテの前身の「MAMADAYS(ママデイズ)」をリリースした2016年当時と比較して、子育てをパートナーとシェアする方が増えていることがユーザーの利用動向から明らかになっています。仕事を通じて新たな“当たり前”に触れることで、自身の認識をアップデートしやすい環境であることは間違いないですね。
こうした背景を基に、今後も育業の推進に注力していきたいと考えています。
―サービス利用動向という具体的な数値で、傾向の変化が把握できているのですね。
三ツ中:以前は半分ほどだった共働きユーザーの割合が直近では7割を超えています。男性のユーザーも徐々に増加しており、アプリの育児シェア機能の活用が、開始当初から2.6倍に増えております。共働きのご家庭ほどパートナー同士で育児をシェアして負担を軽減するニーズが高いと思いますので、私たちも育児の困りごとを解消できるサービスを提供するため日々新たな機能やコンテンツの検討を続けています。
私たちが2023年にMAMADAYSからトモニテへとリブランディングしたのも、そうした社会的変化が背景のひとつです。私たちがサービスをお届けしたい相手が、ママだけでなく“家族”のみなさんだということを改めて発信していく意図もありました。
―男性育業や育児のシェアが浸透するために解消すべき課題はあるのでしょうか?
三ツ中:パートナー同士や実家のご両親など複数人で育児を行う際、“育児の情報の共有”が欠かせません。「何時に何mlミルクをあげたか」や「何月何日に予防接種に行く」などの情報を育児に関わる人たち全員が確認できると、育児のシェアがスムーズに行えるようになるかと思います。
トモニテのアプリでも「育児記録」機能やカレンダー機能があり、ミルクをあげたりおむつを替えた時間や様々な予定をアプリに記録しておくことが可能です。ミルクをあげた時間を口頭で伝えそびれても、アプリを見れば何時にあげればいいのか把握できる。育児をシェアする時代だからこそのニーズではないかと思っています。より育業しやすい環境を提供し続けることは、社会にとっても当社にとっても、解決すべき重要な課題と考えています。
経験者に聞いた、育業のエピソード

部長・堀田 敏史さん
―「育業する」と周りに伝えた際のことを教えてください。
デリッシュキッチンカンパニー サービスグロース部/トモニテカンパニー サービスグロース部 部長・堀田敏史さん(以下、堀田):私は2人目の子供の出産に合わせて36日間育業しました。当社では管理職のメンバーの育業も増えてきていますので、私が育業の意志を社内で伝えた際にも、想像していた以上に人事関連の手続きやチームメンバーとの業務調整がスムーズでした。このような経験から社内で男性の育業が当たり前になっている雰囲気を実感しました。
―育業中の過ごし方はイメージしていた通りでしたか?
堀田:育業中は育児をしたり、上の子の保育を担当したりしました。二度目の育児で経験もあったので私も妻も育児で手一杯になることなく、成長する子供たちとの時間を過ごすことができてよかったと感じています。また復職した際には業務を引き継いだメンバーたちが経験を積んで頼もしくなっていて、家だけでなく会社でも成長を目の当たりにして驚きと喜びを感じることができました。
ママ・パパ・社会。みんなで子育てを行う社会に。
―三ツ中さんご自身も育業を経験されたとお聞きしました。
三ツ中:はい。私は2人子供がいて第一子は里帰り出産でした。第二子の出産の際には上の子の保育園があったため里帰り出産をせず、夫が1ヶ月ほど育業しました。育業中、夫は主に私が出産入院する際の上の子の世話や保育園の送り迎えなどを担当しましたが、私の負担をシェアするだけでなく子供の心のケアの面でも夫の育業は大切だったと思います。下の子が産まれたとき、上の子も2歳でまだ母親離れできていない年齢でしたので、私が上の子と遊んでいる間は夫が下の子の世話をするなど、私が下の子につきっきりにならないよう調整できたこともよかったと感じています。
また私自身、育児は働くことと同じぐらい大変だと感じていたので、「育児は『休み』ではなく『未来を育む大切なしごと』」という育業の考え方には非常に共感を覚えます。トモニテでもこうした考え方の推進のお手伝いができたら嬉しいですね。

―企業が育業を推進するためのポイントはあるのでしょうか?
三ツ中:上長が率先して育業することではないでしょうか。上長自身が育業に積極的な姿勢を見せることにより、社内で育業に前向きな雰囲気が作られ、部下のみなさんも「自分も育業しよう」と思う職場になっていくかと思います。
また、上長が出産を控えたパートナーのいる社員に声掛けすることでも、「育業に理解のある上長」という認識を周囲に持ってもらうことで育業推進につながるのではないかと考えています。当社でも上長の声掛けで育業しやすい雰囲気の醸成を図っています。
―今後の目標を教えてください。
三ツ中:トモニテの名前の通り「ともに手をとりあえる社会になる」ことが目標のひとつです。トモニテを通じて育児のシェアを容易にすることで男性育業も推進しながら、子育ては社会全体で行うもの、という認識の浸透を後押ししていきたいです。また私たちエブリーの社内でも、世の中の育業推進の最新事例に触れることで意識のアップデートを図りながら、男性の育業取得率100%を維持しつつより良い働き方を模索していきたいと思っています。
記事の内容は掲載時点の情報に基づいております。