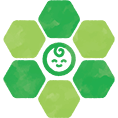掲載日:2025年7月11日
SBSホールディングス株式会社
育業取得率100%を達成!育業を推進し、家族の絆を未来に運びたい
輸配送から保管、流通加工までを手掛ける総合物流企業、SBSホールディングス株式会社。物流支援や不動産事業も展開し、ニーズに応じた物流センターや倉庫の開発も行っています。また、職場環境については男女ともに育業取得率100%を達成し、さらなるライフワークバランスの推進に向けた取組を進めています。
そこで、今回は、同社人事部 労務厚生課長である奥谷 茂典(おくたに しげのり)さんと、昨年育業された情報システム1部 共通システム課の石川 直道(いしかわ なおみち)さんに、育業推進に向けた工夫や体験談についてお話を伺いました。

育業対象者に対して制度をわかりやすく案内! 社内の認知拡大から育業取得率100%を達成
―貴社における育業の状況について教えてください。
人事部 労務厚生課長 奥谷 茂典さん(以下、奥谷):2023年に育業取得率100%を達成し、以降、男女ともに取得率100%を継続しています。ただ期間については、女性は1年間程度育業する方が多いのに比べ、男性は平均すると1週間程度にとどまっている状況です。そのため、全ての社員がより長く育業できるよう、さらなる推進が必要だと考えています。
―育業取得率100%を達成した背景にはどのような制度や仕組みがあったと思いますか?
奥谷:もともと、在宅勤務や短時間勤務などは社内でも活用する人が多かったです。しかし、育業の認知度については低いことが課題でした。 そのため、育業対象者に向けて制度を積極的に案内するよう努めました。具体的には、必要な人が制度を身近に感じ、スムーズに育業できるよう育業対象者への制度等の個別周知・意向確認の際、できるだけわかりやすい内容で行うよう工夫しています。ほかにも、育業するハードルを少しでも下げられるよう社内で必要な手続きをまとめて案内するなど育業当事者がやらなければならないことを明確にしています。
また、法改正がある度に、その内容に沿った制度をきめ細やかに周知したことで社内の制度に対する認知も拡大できたと考えています。
そして、こうした取組が育業取得率100%につながったのではないかと感じています。
ーその他、子育てを支援するための制度についても教えてください。
奥谷:育児中の方のみを対象とした制度ではありませんが、コロナ禍を機に、フレックスタイム制度(※)と在宅勤務制度を導入しました。小さい子供を持つ社員は、短時間勤務制度とともに、こうした制度を活用できるのでそれぞれの生活に合わせて働きやすい環境が整っていると思います。
※フレックスタイム制度とは…
社員が始業・終業時間を自由に設定できる制度のこと。SBSホールディングスでは、10時~12時を社員が必ず勤務しなければならない時間(コアタイム)として定め、繁忙時や自身の都合に応じて働きやすい勤務時間を設定しています。

ーこうした制度を導入したことで、社員からの声はありましたか?
奥谷:「働きやすくなった」「助かっている」という声は多いです。中には、育児と仕事の両立を考え、ほぼ全日在宅勤務で働いている社員もおります。
また管理職からも、「子供のいる社員も、時間を効率的に使って、高いパフォーマンスを発揮してくれている」との報告を受けています。
育業を経験して得た気づきとは?

ーここからは、実際に育業を経験された石川さんにお話を伺います。
育業しようと思った理由を教えてください。
情報システム1部 共通システム課 石川 直道(以下、石川):もともと、妻が里帰り先から自宅に戻ってくるタイミングで、数日間の休暇を取ろうと考えていました。育業に関する制度は知っていたものの、手続きが面倒そうだと思っていたので、最初は使うつもりはなかったです。
しかし、人事の方から制度の利用を勧められ、手続きも簡単だと教えてもらったこともあり、6日間の産後パパ育休を取得すると決めました。実際、手続きはすぐにできたので安心しましたね。
ー育業することに対して、周りの反応はいかがでしたか?
石川:周りのメンバーは業務をサポートしてくれ、上司も快く送り出してくれました。「もっと育業しなくて良いのか?」と心配してくれたほどです。
ちょうど担当しているプロジェクトが佳境だったため、自分でやり切りたいと思っていたこともあり、6日間という期間にしましたが、長い期間の育業でも応援してくれる雰囲気がありました。
ー実際に育業された感想を教えてください。
石川:生まれたばかりの赤ちゃんはもちろんかわいいですが、約3時間おきに起きるので、昼も夜も関係なくお世話をしなければならないことが大変でした。
仕事をしていれば、勤務時間中は一時的に育児から離れられることで心身が休まる面もあると思います。しかし、1日中子供と向き合っていると、心の逃げ場がないということを痛感しました。育業しなければ、この大変さは理解できなかったと思います。
また、私にとって初めての子育てなので、泣きやまないときには泣いている理由がわからずに戸惑ったり、焦ったりもしましたね。

―育業する前に考えていたイメージとギャップはありましたか?
石川:子供が生まれる前は、育業というと「我が子と濃密な時間を過ごせて幸せな時間」「すぐそばで成長を見られることが嬉しい」といったポジティブな声を聞くことが多く、プラスのイメージが強かったです。
しかし、実際に経験してみると思った以上に育児が大変で、育業が“休暇”ではないことを実感しました。6日間という短い期間でも心身ともに疲れましたので、長い期間育児に全力で向き合っている親の負担は本当に大きいと改めて思いました。
ー育業を経験して、ご自身に変化はありましたか?
石川:これまで、男性の育業は“したい人がするもの”であり、人によってはしなくても良いと思っていましたが、今は「子供を持ったすべての人におすすめしたい」と思っています。
会社の仕事を一旦離れて育児に専念する時間は、育児の理解を深める貴重な機会となりました。これは家族の一員として子育てをしていく上で、絶対に必要な経験だったと感じています。 今回は6日間でしたが、次の機会があれば、数ヶ月間は育業して育児に向き合いたいです。出産のタイミングを予測しながら、事前に準備することで、長期間の育業も考えています。
育業取得率100%達成!次は、‟育業期間の充実”へ
ー育業の推進にあたり、今後の展望を教えてください。
奥谷:育業取得率100%の達成を維持しながら、今後は育業期間をもっと長くできるように改善していきたいと考えています。
そのため、これからはさらに不明点を気軽に聞きやすい環境を作り、質問があればしっかりフォローする体制を整えたいと思っています。
また、育業対象者だけでなくその上長にも積極的にアナウンスし、育業に対する理解と協力を得ることで、組織全体でさらに育業しやすい環境を整えていきたいです。
―育業推進への意気込みを一言お願いします。
奥谷:私たちは物流の会社として、普段は物を運ぶ仕事に携わっていますが、育業の推進によって物だけではなく、家族の絆や笑顔を運び、届けていきたいと考えています。また、社内で育業を進めていくことにより社員が安心して働ける環境整備や企業としての持続的な成長にもつながると嬉しいです。
これからも育業を推進し、多くの人が笑顔で過ごせる明るい未来を築いていけるよう、努めていきたいです。
――ありがとうございました。
記事の内容は掲載時点の情報に基づいております。