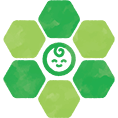掲載日:2025年9月12日
三菱電機トレーディング株式会社
育業とともに広がる、フレキシブルな働き方。一人ひとりが自分らしく働ける未来へ
三菱電機グループの商社として、電子部品や設備機器、オフィス用品などを国内外に届けている三菱電機トレーディング株式会社。資材の調達から販売、国際取引まで幅広く手がけ、ものづくりや暮らしを支えています。
同社では、育児と仕事の両立を可能とする制度を整えるとともに、制度活用に向けた様々な取組を行い、誰もが育業しやすい職場環境づくりを進めています。
そこで、今回は、総務部 労政福祉グループ グループマネージャーの柴崎 有希(しばさき ゆうき)さん、加藤 沙絵子(かとう さえこ)さん、実際に育業を経験した総務部 人事研修グループの田中 智也(たなか ともや)さんに、育業の取組や育業したからこそ見えてきた気づきについてお話を伺いました。

5年間で男性の育業取得率が83%までアップ!広がった選択肢と変わる価値観
―貴社における育業の状況について教えてください。
総務部 労政福祉グループ加藤 沙絵子さん(以下、加藤):男性の育業を推進し始めた2018年時点では0%だった男性育業取得率が、2024年度には83%となるなど、男性の育業取得率はこの数年で大きく伸びています。
また、育業期間についても、数ヶ月から半年 などの長期で育業する男性社員が増えてきています。
―男性の育業推進に取り組み始めた背景を教えてください。
総務部 労政福祉グループ グループマネージャー 柴崎 有希さん(以下、柴崎):社員がより働きやすい会社とするため「子育てサポート企業」として厚生労働大臣から“くるみん“の認定を受けることを目指し、男性の育業についても2018年頃から推進してきました。
社長から、「まずは2025年までに男性育業取得率70%をめざす」というメッセージが全社員に発信されたことで、会社全体としての意識改革が一気に進んだように感じています。

加藤:育児と仕事の両立支援制度の整備や制度を利用しやすくするための様々な取組を行ったことで“くるみん“には2020年に認定され、あわせて社内での育業への理解も進みました。
制度も周囲の理解も。“使える”育業支援を目指して
―育業の推進や育児と仕事の両立に関する社内制度について具体的に教えてください。
加藤:法律上の制度はすべて整えた上で、独自の支援策も充実させています。
例えば、開始から5日間、有給で育業できる制度や育業当事者の仕事を引き継いだ社員の給与に加算を行う「サポート加算制度」の導入などです。また、育業する社員の仕事を分担するため、定年退職した元社員に声をかけて一時的に業務を手伝ってもらうことも行なっています。
その他、復職後も働きやすい環境をつくることを目的に、短時間勤務についても小学6年生の年度末まで延長して利用できるようにしています。
在宅勤務については、一般社員は週2回までですが、育児中の社員にはそれ以上の利用を認める「在宅勤務特例」を設けています。今年から1時間単位の時間休暇が取得できるようになったことも、育児中の社員から柔軟に時間を調整できると好評です。
また、子供1人につき月2万円の育児支援金を、22歳まで支給しています。
柴崎:ただ、制度がどれだけ充実していても、そうした制度を実際に使用できる雰囲気がなければ、なかなか活用にはつながりません。
そこで、新たに管理職になった社員に対して育業に関する研修を実施したり、管理職全体を対象としたセミナーを開催したりすることで、育業への理解を深めてもらうようにしています。
加藤:また、社内ホームページでは、育業に関する制度の改正内容のほか、育業を経験した社員のアンケート結果、制度を利用した社員へのインタビュー、育業した男性社員の座談会なども掲載し、積極的な情報発信を行っています。
こうした発信を通じて、育業やその後の働き方を具体的にイメージしてもらい、無理なく制度を活用できるようにしています。
―かなり制度が充実していますが、それらの制度はどのようにして生まれたのでしょうか?
柴崎:年に2回、社員が会社への意見を出し合う「代表会議」という場があるのですが、そこで出た声を制度に反映するようにしています。時間単位での休暇の導入や、短時間勤務の期間延長といった仕組みは、この会議での要望から実現したものです。
加藤:こうした取組もあり、会社全体として性別に関係なく育業しやすい雰囲気が少しずつ作られてきたことで、育業取得率や育業期間の伸びにつながっていると感じています。

―長期間育業した社員へのサポートがあれば教えてください。
柴崎:長期間の育業から復職する社員には、上長との「復職面談」を設けるようにしています。この場を通じ、育児と仕事を無理なく両立できるように、今後の働き方についてすり合わせています。勤務時間や業務量をどうするのか含め、一人ひとりに合った働き方について一緒に考えることを大切にしています。
育業で深まった家族の絆。支えてくれたのは、職場の笑顔と安心感
―ここからは、実際に育業された田中さんにお聞きします。育業しようと思った理由を教えてください。
総務部 人事研修グループ 田中 智也さん(以下、田中):私も妻も地方出身で、出産後に両親からのサポートを受けることが難しい状況でした。また、妻も復職予定だったので、夫婦で育児と仕事を両立するべく、妊娠がわかったタイミングで話し合って育業することを決めました。
―職場の反応はいかがでしたか?
田中:私の部署は年単位のプロジェクトも多く、私が抜けることで周囲に負担をかけてしまう部分もあったと思います。それでも育業すると伝えたときは、誰も嫌な顔をせず、笑顔で「おめでとう!」と言ってもらえたのが、本当に嬉しかったです。
上長に妻の妊娠を報告したときも、「おめでとう!育業はどれくらいする?」と、育業することを前提に話をしてくれたので、6か月という長期間の育業も相談しやすかったです。

―実際に育業した感想を教えてください。
田中:生後3か月くらいまでは、まとまった睡眠もとれず、心身ともにつらい時期が続きました。だんだんと子供の睡眠リズムが整い、私が笑いかけると笑い返してくれたり、話しかければ「あー」「うー」と声を返してくれたりするようになってからは、子育ての喜びや楽しさを強く感じるようになりました。子供の成長にゆっくり向き合える時間を持てて本当に良かったと思っています。

―育業を経験したことで変化はありましたか?
田中:最も大きく変わったのは、妻との関係です。2人で一緒に育児に向き合うことで、パートナーとしての絆が深まったように感じています。2人揃って育児にしっかり向き合えたことは、これからの家族関係にとっても、非常に大きな意味があったと思います。
―育業する際に、あって良かったと感じた社内の制度や取組はありますか?
田中:会社から発信される男性育業に関するアンケートやインタビューの内容は、どのように育業するか考える上で大変参考になりました。年々、社内の育業期間が伸びていることもわかりましたし、長く育業した男性社員のメッセージで「これから子供が産まれる方には、絶対に育業することをおすすめしたい」というものも多かったので、前向きな気持ちで育業することを決められました。
また、こうした育業中のエピソードを知ることに加え、育業する際に上司が親身になって相談に乗ってくれたことで育業することのイメージも湧き、心理的に育業しやすくなりました。
今後、状況に応じて在宅勤務特例や時間休暇制度の利用も検討しています。制度が整っていることで育業と働き方の選択肢が増えているのは非常に心強いです。
一人ひとりに合った育業へ。フレキシブルな制度設計と、支え合いが根づく職場を目指して
―育業を推進することで、会社にどのようなポジティブな効果がありましたか?
加藤:以前は、男性の育業は特別なものという印象が強かったのですが、最近は「子供が生まれたら育業するのが自然」という雰囲気が、社内に広がってきていると感じます。
田中:私は人事の採用を担当しているのですが、学生から育業について質問されることがとても多いです。その際に、当社の制度や取組を紹介すると非常に反応が良く、採用の場でもプラスに働いていると感じています。

ー育業の推進にあたり、今後の展望を教えてください。
柴崎:育業する本人だけでなく、周りのメンバーや会社全体で子育てを応援し、支え合える職場にしていきたいと考えています。
そのためにも、一人ひとりの状況や社会の変化に応じて、制度や仕組みをフレキシブルに見直しながら、より働きやすい環境づくりを進めていきたいです。
加藤:実は私自身も、育業の大切さを身をもって感じた経験があります。
出産後、里帰りから戻ってすぐに子供と2人きりの生活が始まり、心も身体もつらくなって夫に相談しました。そのとき、夫が3日間育業してくれたのですが、たった3日だけでも本当に救われたのを覚えています。
だからこそ、これから出産や育児に向き合う社員にも、自分にとって必要なタイミングで、無理なく育業してほしいと思っています。お互いに支え合える環境を整え、より働きやすく、あたたかい会社をつくっていきたいです。
――ありがとうございました。
記事の内容は掲載時点の情報に基づいております。