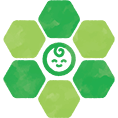掲載日:2025年10月2日
住友ベークライト株式会社
声を制度に、制度を風土に。育業から広がる、多様な働き方と助け合う職場づくり
フェノール樹脂に代表される高機能プラスチックのパイオニアとして、エレクトロニクスや自動車、医療など幅広い分野のものづくりを支えてきた住友ベークライト株式会社。 技術と人の力を両輪に、社会に貢献するものづくりを目指す同社では、ライフステージが変わっても、社員が安心して働き続けられる職場づくりに向け、育業を積極的に推進しています。
そこで、今回は、人事本部DE&I推進室 企画推進チームリーダーの平井 美帆子(ひらい みほこさん、総務本部 コーポレート・コミュニケーション部の田上 沙彩佳(たのうえ さやか)さん、実際に育業を経験した人事本部 人材開発部 人事グループの筒井 皓也(つつい ひろや)さんに、育業の取組や育業したからこそ気づけたことについてお話を伺いました。

なぜ、これほど伸びた? 変化の背景にあった取組
―貴社における育業の状況について教えてください。
人事本部DE&I推進室 企画推進チームリーダー 平井 美帆子さん(以下、平井):以前から育業の制度自体はあったものの2022年度の男性育業取得率は26%と低いことが課題でした。
そこで、性別に関係なく「育てること」と「働くこと」が両立できる職場環境づくりに向け、2024年度から始まった中期経営計画で「男性育業取得率を2030年までに90%にする」という目標を掲げ、男性の育業を積極的に推進してきました。
その結果、男性育業取得率は2024年度に84%となり、平均育業期間も83日となりました。男性育業はここ数年で社内へ急激に浸透しています。
―ここまで育業が浸透した理由を教えてください。
平井:男性育業をテーマにした教育を希望者向けに実施するとともに、その際のアンケート結果を社内に共有することで教育を受講していない社員にも会社の方針が伝わるようにしています。

人事本部 人材本部 人材開発部 人事グループ 筒井 皓也さん(以下、筒井):制度的にも2022年10月から出生時育児休業(産後パパ育休)の初めの5日間を100%有給化しています。これによって育業することへの心理的なハードルが下がり、育業取得率の向上につながったと感じています。
平井:その他、育業当事者の体験談や平均育業期間を社内に発信する取組も行っています。平均育業期間は現在、83日となっていますが、こうしたモデルケースを紹介することにより育業をためらっていた社員が実際に育業することをイメージでき、「長く育業することも可能だ」という意識の変化が生まれたのだと思います。
ただ、部門によって育業しやすさに差があるという課題もあるため、育業や働き方改革に積極的な事業所へのヒアリングや意見交換を通じて、有効な取組を社内報やポータルサイトで共有することで、誰もがより育業しやすい環境整備に取り組んでいます。
制度をつくり、声を聞き、広げていく。育業を支える取組の裏側
―育業や育児と仕事の両立に関する社内制度について、具体的に教えてください。
筒井:育業は子供が2歳まで、短時間勤務は末子が小学校6年生まで利用可能です。また、時間単位での年次有給休暇やフレックスタイム制度も整備しており、個人に合わせた柔軟な働き方ができるようにしています。
当社では年に一度、労働組合から会社に対して要望を出す機会を設けていて、2歳までの育業制度も、こうした要望をきっかけにライフワークバランスの観点から2014年に導入したものです。

平井:他にも「子供の都合で急な早退やお休みがあるため、短時間勤務の社員に期日がある仕事を任せづらい」「育児と両立するため、在宅勤務制度を活用しているが決められた上限日数では足りない」といった社員の声を反映し、育児・介護中の社員については在宅勤務日数の上限を月8日から月12日に拡大しました。
―社内への情報発信についても詳しく教えてください。
平井:最近は社内ポータルサイトや社内報などでも育業に関する情報を積極的に発信しているほか、より実践的な支援策として『キャリアと育児の両立支援ハンドブック』を作成しました。
総務本部 コーポレート・コミュニケーション部 田上 沙彩佳さん(以下、田上):社内ポータルサイトには、制度変更のお知らせだけでなく、育業当事者へのアンケートや、ライフワークバランスを実現するための「両立の工夫」を社内から募集し、掲載しています。中には、スマートAIなどのデジタルツールを活用して育児と仕事を両立している社員もいて、勉強になったという声が届いています。

―『キャリアと育児の両立支援ハンドブック』についても詳しく教えてください。
平井:社内規則だけでは伝わりづらい内容を、図を交えてわかりやすく整理し、PCを持たない社員も含め、誰でも手軽に情報へアクセスできるようハンドブックとしてまとめました。女性社員向け、男性社員向け、上司向けの3種類があり、「この時期には何をすべきか」「育児と仕事の両立に向けた工夫はどういったものがあるか」といった実践的な情報に加え、上司向けには、部下のモチベーションを下げないためのマネジメントについても記載しています。
制度を知るだけではわからなかった、育業での気づきと喜び
―ここからは、実際に育業された筒井さんにお聞きします。
育業しようと思った理由を教えてください。
筒井:私自身が人事という立場で、業務として育業制度に関わることも多かったため、以前から「いつか自分も育業したい」と考えていました。実際に妻の妊娠がわかった際、妻と話し合って、子供の世話を夫婦で行うべく、育業することを決めました。 まずは出産のタイミングで出生時育児休業(産後パパ育休)で5日間育業しました。その後、子供が生後1ヶ月頃になり、妻が里帰りから戻ってくるタイミングから約6ヶ月間、育業しました。

―周囲の反応はいかがでしたか?
筒井:男性の育業自体は広がりつつあるものの、6ヶ月間という長期の育業については、「すごいね」「長いね」「そんなに育業できるんだ」と驚かれました。
職場のメンバーは「頑張ってね。仕事はこっちでやっておくから!」と快く送り出してくれ、とてもありがたかったです。
―実際に育業した感想を教えてください。
筒井:首も座っていない小さな命を預かることへの怖さや不安はもちろん、夜中でも定期的に起きて泣く子供のおむつ交換やミルクなど、大変なことが多くありました。しかし、毎日が初めての連続でそれ以上に楽しかったです。目に見える成長を間近で実感し、初めての時間をみんなで分かち合えたことが、本当にかけがえのない経験だったと感じています。
今は復職して日中は一緒にいられない時間が増えましたが、帰宅後に顔を合わせて「ただいま」と言うとにっこり笑ってくれます。「育業せず夜しか顔を合わせられなかったら、こうはならなかったかもしれない」と思うこともあります。6ヶ月間一緒に過ごしたことで、家族としてしっかり認識してくれていることがうれしいです。
少しでも家族の時間をとれるように、以前よりも時間の使い方や業務の効率を強く意識して働いています。

―復職して大変だったことはありますか?
筒井:やはり6ヶ月もの間、仕事から離れていると、業務に関わるさまざまなことを思い出すことから始まるので、大変でした。でも周りのメンバーや上長にたくさんのサポートをしていただいたおかげで、焦らずに仕事に馴染んでいくことができています。
―あって良かったと思う社内の制度や取組はありますか?
筒井:最初の5日間、100%有給となる出生時育児休業 (産後パパ育休) 制度のおかげで、給与面への影響はあまりありませんでした。
もちろん自治体などからの支援もありますが、収入が減るとなると心理的ハードルが上がってしまいますので、とても助かりました。
現場へ、全社へ。育業を支える動きが、さらに広がっていく
―育業の推進にあたり、今後の展望を教えてください。
平井:最近では、人事本部が発信する施策だけでなく、各地の事業所が現場でのニーズを踏まえ、自ら考えて実施する取組も出てくるようになりました。当社は各地に事業所や工場があるため、それぞれの状況に合わせて自律的に取り組むことが理想的な姿だと思っています。こうした取組を共有し続け、さらに厚みのある活動に発展させていきたいです。
田上:社内ポータルサイトでも「両立の工夫」などの投稿が増えてきていて、みんなでアイデアを共有しあい、支え合いながら育児と仕事を両立していこうという雰囲気ができてきたように感じ、とても嬉しく思います。
平井:引き続き、性別を問わず「育てること」と「働くこと」が両立できる職場環境に向け、育業を推進していきたいと思います。
――ありがとうございました。
記事の内容は掲載時点の情報に基づいております。