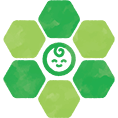掲載日:2025年3月21日
日本ケミファ株式会社
まずは取り組んでみる!
男性育業“義務化”の制度導入で、全社員が働きやすい職場環境の実現へ。
日本ケミファ株式会社は、1950年の創業以来70年余りにわたり製薬企業として歴史を重ね、現在は新薬とジェネリック医薬品の両分野を取り扱う製薬企業として独自のポジションを築き上げています。同社では女性の営業職(MR ※1)が多数在籍しており、以前から社員が男女の垣根なく活躍できる環境作りに取り組んできたといいます。そんな中で現在注力している取組のひとつが、“男性育業の推進”です。
今回は、同社 人事部長兼社長室長の宮田 裕文(みやた ひろふみ)さんと、人事部課長の服部 靖代(はっとり やすよ)さんにお時間をいただき、同社の目指す男性育業制度のかたちや働きやすい職場環境についてお話を伺いました。
※1:「Medical Representative(医薬情報担当者)」病院や開業医への情報提供を通して、製品普及のための情報収集と新規採用依頼を行う仕事
当時の中堅企業では異例の“育業義務化”を決断
―男性の育業推進に注力したきっかけや背景を教えてください。
人事部長兼社長室長 宮田裕文さん(以下、宮田):男性の育業を本格的に推進しはじめたのは2019年度からです。同年に「パパ・クオータ制度」※2を導入し、全男性社員に対して育業を義務化しました。育業期間は、導入当初は3日間以上、現在は5日間以上としています。
※2:子供が産まれた男性社員に対し、子供が2歳になるまでに規定日数の育業を義務付ける制度。期間中は有給休暇扱いとなり会社から給与が支払われる。
人事部課長 服部靖代さん(以下、服部):この制度の導入時には、新しく子供が産まれる社員だけでなく、2歳未満の子供を持つ社員も対象としました。またこの制度の導入と同時に、女性が育業する際にも男性と同じ日数だけ有給休暇扱いとなるようにしました。男女ともに会社が育業を金銭面で支援するかたちとなります。
宮田:育業を義務としたこともあり、男性も含め育業取得率は100%です。育業の日数は部署によってばらつきもありますが平均で8.7日(2023年度実績)、これまで最も長かった例では3ヶ月育業する男性社員がいました。男性の育業が社内でさらに浸透することで、日数をもっと延ばしていきたいと思っています。
男性育業の義務化の狙いは、男性社員にも育業に対する意識を高めてもらうことです。それまで社内で育業するのは女性社員がほとんどで、男性社員向けにも育業の制度はありましたが、活用されていないのが実状でした。2016年にグループ内で初めて男性で育業する社員が誕生しましたが、その後も「男性も育業するのが当たり前」という認識にまでは至りませんでした。
そのため当時はまだ弊社のような中堅企業では「義務化」までは進んでいなかったと記憶していますが、社内の意識改革のためにも思い切って導入を決めました。

―社内の認識を変えるため、新たな一歩を踏み出したわけですね。
宮田:弊社では多くの女性MRが活躍しており、結婚や出産といったライフイベントを経ても働き続けられる環境を整備することが不可欠でした。出産後に復職してからも働きやすいよう、営業先に行く前に営業車で子供を保育園に送れるようにしたり、女性MRからの要望で営業車の中にチャイルドシートを設置できるようにしたりするなどの改善を続けています。
男性の育業推進も、「女性だけに育児の負担がかかっている」状況を改善して男女ともに活躍できる環境作りの一環だと考えています。また、弊社社長がこういった取組を積極的に応援してくれるため、社内の働き方をより良くできるアイデアはどんどん取り入れていける環境にあることも大きいと思っています。
服部:フレックス勤務や裁量労働制度※3を早くから採用しましたし、業界の中であまり高いほうではなかった有給休暇取得率の向上のために有休の事前登録制度※4の導入もしました。「様々な経験を通じて仕事の視野を広げる」目的でボランティア休暇も取り入れています。
※3:業務の性質上、業務遂行の手段や方法・時間配分等を労働者の裁量に大幅にゆだねる必要がある業務に適用でき、対象労働者をその業務に就かせた場合、実際の勤務時間に関わらず、労使であらかじめ定めた時間(同社の場合は所定労働時間)働いたものとみなす制度。
※4:年次有給休暇のうち毎年10日間の取得を義務化し、年度の始めに取得時期を登録させる制度。
―新しい取組をはじめやすい社風の中で、男性育業を推進させる際の阻害要因はありませんでしたか?
宮田:制度として推進されてはいるものの、現場には「実際に育業することへの不安」もあったようで、業務を引き継ぐ周囲の負担や、自身の評価・キャリアへの影響を懸念する声が多く聞かれました。

服部:評価やキャリアについては、育業前や復職後の面談で上司から説明をしてもらい不安を解消してもらっています。男女ともに復職後の面談を通じて今後の働き方を相談しながら一人ひとりに合わせたキャリアプランを考えるように心がけています。復職後も高いパフォーマンスを発揮している社員については、昇格要件等だけによらず昇格を検討する、というケースもあります。
一方で業務を引き継ぐ負担については、製薬関連の職種や事務職を含む内勤の社員と、外回りの多いMRの社員ではまだ育業の日数に差があるのが現状です。
宮田:チーム内で業務をシェアしやすい内勤の社員と比べると、一人ひとりが担当エリアを持っているMR職のほうが業務の引継ぎが難しく、育業する日数が短くなりがちです。引き継ぐ負担をどのように軽減していくかが、これから解決していくべき課題と認識しています。
制度の導入後も、柔軟な対応でより良い育業を実現する。

―男性育業について、今後進めていきたい取組を教えてください。
宮田:具体的な取組方法の検討はこれからですが、現在8.7日の育業の平均日数をもっと延ばしていけたらと思います。また、日数だけでなく多様な働き方の要望にも対応できるようになっていきたいと思っています。
服部:女性社員のケースではありますが、家庭の事情で地方や海外に移住した後もテレワークを利用して働き続けている社員もいます。「夫のアメリカ赴任に付き添うけれど、自分の日本ケミファでのキャリアも止めたくない」と本人が希望していたので、所属部署とも相談のうえで実現しました。
―とても柔軟な対応ですね。
宮田:弊社の育業制度はまだまだ発展途上です。先にも述べたようにMR職の引継ぎ方法をどのように最適化するかなど、様々な点を改善していく必要があります。
ですが育業の推進は必ず社員の働きやすさの向上につながっていくことですので、諦めるという選択肢も、現状のまま停滞するつもりもありません。育業の事例を増やすことで「このケースではこんなポイントが良かった」などのノウハウを社内に蓄積し、検討を重ねながらより良い制度になるよう取り組んでいきたいと考えています。
服部:多くの男性社員が育業を経験することで、「仕事と育児の両立」への理解も深まると思います。自分自身が過去に育業した経験から、他の社員の育業で業務を引き継ぐ際にも「前に自分もフォローしてもらったし、今度はフォローする側で頑張ろう」とお互い様の気持ちで対応できるようになり、今まで以上にチームワークが向上すると思います。
宮田:チームの雰囲気が良い働きやすい職場であれば従業員の満足度も上がり、優秀な社員の獲得や定着につながり、ひいては業績への好影響や、企業価値の向上にもつながっていくものと期待しています。
記事の内容は掲載時点の情報に基づいております。