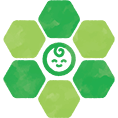掲載日:2025年3月24日
株式会社東京スター銀行
社内報で育業経験者の声を紹介し、制度の浸透を促進
妊娠前から就学後まで、様々な段階で子供との絆の強化を支援する想い。
株式会社東京スター銀行は、銀行では珍しく中途採用者が約8割を占め、他業界経験者や外国籍の行員も数多く在籍する銀行です。そんな同行では、男性育業の推進についてどのような取組を行っているのでしょうか。
同行 人事部人事管理アシスタントヴァイスプレジデントの池田 愛さんと、2023年に育業を経験された経営企画部経営企画アシスタントヴァイスプレジデントの酒井 陽一朗さんにお話を伺いました。

育業のモデルケースを社内報で発信
―御行の男性育業の状況を教えてください。
人事部人事管理アシスタントヴァイスプレジデント 池田愛さん(以下、池田):法改正により分割して育業できるようになった2022年度に男性の育業取得率が100%に達するなど、ここ数年で社内に広く浸透してきた実感があります。
2023年度は1年間で91.7%、11人の男性行員が育業しており、平均日数は2週間程度でした。2024年4月からの半年間は88.9%、8人、平均日数は50日以上となりました。平均日数は時期によって大きく異なる傾向にあり、ちょうど2~3ヶ月や半年間など長期間育業される男性行員が多いタイミングだったのですが、今までにない長期の日数に私たち人事スタッフも少々驚いています。

―男性育業が浸透していった理由はなんでしょうか?
池田:当行の男性育業推進は、女性活躍推進の取組から始まっています。2013年頃からダイバーシティ・女性活躍推進プロジェクトがスタートし、女性の仕事と家庭(主に育児)の両立を目指していく中で“男性の育児”についても意識していくようになりました。
さらに2018年から2020年にかけて「改正次世代育成支援対策推進法」に基づく行動計画の取組の中で、役員や各部門上司のイクボス宣言の実施をはじめ、全行が一体となって育業のための様々な仕組み作りやサポート体制の強化を図ってきました。併せて男性育業推進のため、男性行員から配偶者が出産した旨の申告があった際に対象者一人ひとりに対して、上司同席のうえ当行の育業制度の内容や手続き方法などを具体的に案内したり、社内報で育業した男性行員のインタビューを連載したりするなどの施策も実施しています。
育業の当事者だけでなく周囲にも協力や連携を促す取組を推進した結果、2021年に優良な子育てサポート企業として「プラチナくるみん」認定を取得できたのかなと思います。
―インタビューではどのような方を取材されるのでしょうか?
池田:1週間以上育業したり、「出産休暇」や年度内に有給休暇を5営業日以上連続して取得する「連続休暇」など様々な休暇制度を併用して育業した行員をはじめ、モデルケースとして参考にしやすい社員の体験談をインタビューするようにしています。
経営企画部経営企画アシスタントヴァイスプレジデント 酒井陽一朗さん(以下、酒井):実は私も復職後にインタビューを受けたうちの一人です。私の場合は連続休暇と併用して約2ヶ月の育業でしたが、男性行員の少ない部署に所属していて育業する世代となるとさらに限られていたため、参考にしやすい事例として人事の目に留まったのかなと思います。
池田:営業部門・営業店のようなフロント部門や管理職として働く行員など、部署によっては育業前の業務調整が複雑・時間がかかりやすい部署もあります。そうした部署で育業した男性行員にも積極的にインタビューして、調整のノウハウを多くの部署に共有できたらと考えています。

―育業を推進するうえでの現状の課題は何ですか?
池田:業務調整が複雑な部署の行員でも、スムーズに育業できるような仕組みづくりや風土の醸成をしていくことが喫緊の課題で、部署の上司や同僚の育業に対する理解と協力が不可欠だと考えています。そのため多くの行員が目を通す社内報に育業のインタビューを定期的に掲載するほかに、産後パパ育休の創設など育児・介護休業法改正が施行される直前の2022年9月には、全行員を対象として改正内容に関するeラーニングを実施し、制度の変更点を周知しました。
最近では出産予定日の半年ほど前から上司や人事部に相談を始めて、計画的に育業する男性行員が多くなってきていると感じます。
酒井:私も育業する際には、半年以上前から上司に相談しました。当行では1月から12月までの期間で年度の目標を設定するため、年末の段階で上司に育業の相談を行い、6月頃から育業することを踏まえた目標設定に調整してもらいました。また、同僚に業務を分担してもらったので、上司や同僚の理解と協力が得られたことにも感謝しています。
初めての育業をポジティブな気持ちで取り組む。
―育業された際のことをお聞かせください。
酒井:私は子供が産まれた2023年の6月下旬から8月いっぱいまで、計48日間育業しました。育業前の業務の引継ぎなども、年頭の目標設定の段階である程度の調整を行っていたため比較的スムーズにできたのではないかと感じています。
子供を育てることは私たち夫婦にとって初めての経験になりますので、育業する際は育児に対する不安もありました。ですが同時に楽しみな気持ちもあって、「“初めての”育児は一度しか経験できないのだから、なんでもエンジョイしていこう」と毎日子供と接していたので、想像していた以上に充実した育業ができたと思います。

―実際に育業を経験されてどのように感じましたか?
酒井:育業中の2ヶ月間は夜泣きや寝かしつけなど体力面で大変なことが多かったですが、1歳半くらいになった最近は立ち上がって言葉も覚え始めたので、食事中にテーブルの上に乗ったり遊びたいアピールをしたりと、子供が成長してくるにつれて“大変なこと”も変わってきました。育児は単なる2ヶ月のイベントではなく、これから先数十年続いていく長期的なことですので、会社や周囲のサポートだけではなく、私たち親の側も育業をスキルアップさせて、仕事と育児を両立させ続けられるようライフスタイルのマネジメントが大事になってくると感じました。
復職後には育業経験者が集まるグループチャットに登録してもらったので、社内の育業の先輩たちとのつながりを持つこともできました。日々の育児の中で新たに出てきた悩みなども、すぐに“先輩”に相談できる、という安心感がありますね。
池田:当行は中途採用者が多いので、行員同士、横のつながりを広げるためのコミュニティとしてもグループチャットを活用してもらっています。また個人のコミュニケーションだけでなく、人事からも育業に関する情報などを発信していますので、何か育業で困ったときに助けになるコミュニティにしていきたいと考えています。
―御行では他にどのようなサポートを行っているのでしょうか?
池田:2023年に新設した男女ともに利用可能な「治療サポート休暇」は、不妊治療や重度疾病の治療の際に使える制度となっており、多くの行員が活用しています。不妊治療と仕事を両立する取組では、行内の有志が自身の体験を基に作成している思いやりの詰まった「仕事と治療の両立のための不妊治療サポートガイドブック」を全行員に案内しているので、当事者だけでなく誰もが安心して制度を利用してもらえるよう努めています。
他にも当行では年に一度、行員の子供たちを本店に招待する「キッズデイ」を開催しています。小学生や未就学児を対象としていて、行員が働いている職場や1階にある銀行の店舗を巡って見学したり、当行役員との名刺交換を体験したりしてもらっています。
保護者の方が普段働いている職場を子供たちに知ってもらうことで、行員のライフ・ワーク・バランスを図ると共に、保護者と子供のつながりを深める一助になればと思い実施しています。

4つのバリューを軸に育業を推進
―男性育業の推進について今後の展望をお聞かせください。
池田:育業取得率は80%以上を維持していきたいです。育業する日数についても2024年の4月から上昇傾向にありますので、今後も長く維持できるよう様々な取組と組み合わせての育業を提案していきたいです。
また、育業は当行の掲げるMission・Vision・Valuesのうち4つのValues
・Integrity
・Professional
・Teamwork
・Caring
にも深く関わってくるものだと思っています。
育業はパートナーとの共同作業であり、職場でも上司や同僚が一体感を持って協力していくため、「Teamwork(チームワーク)」は不可欠です。
加えて、相手を信頼して自身の仕事を任せられる「Integrity(誠実さ)」と、育業する行員に対する周囲の「Caring(思いやり)」も必要になってきます。
そして当行には育業経験者の先輩「Professional(専門的な)」がたくさんいますので、育業1年生でも安心です。
当行の育業は、そうした4つの要素から成り立っていますので、今後もこの4つの要素を中心にして新たな施策や取組を広げていきたいと考えています。

記事の内容は掲載時点の情報に基づいております。