掲載日:2025年8月29日
株式会社インフォテクノ朝日
育業をもっと当たり前に。永く活き活きと働ける環境を後押し
朝日生命グループの情報システム全般を一手に担い、システム設計から運用・保守までを手掛ける、株式会社インフォテクノ朝日。信頼性と利便性を重視し、生命保険のサービス向上に貢献しています。
同社では、育児と仕事の両立に向けて制度を整えるとともに様々な取組を行い、男女ともに育業取得率100%を実現。柔軟な働き方を可能とし、社内の理解促進も図りながら、誰もが育業しやすい環境づくりを進めています。
そこで、今回は、人事部の清水 健一(しみず けんいち)さん、太田 真里子(おおた まりこ)さん、荒井 那津子(あらい なつこ)さん、実際に育業を経験した石川 博志(いしかわ ひろし)さん、西尾 有司(にしお ゆうじ)さんに、育業の取組や現場でのリアルなエピソードについてお話を伺いました。

育業取得率100%達成からその先へ。進化し続ける“働きやすさ”のかたち
ー貴社における育業の状況について教えてください。
人事部 スペシャリスト 荒井 那津子さん(以下、荒井):女性の育業取得率は以前から100%を維持していましたが、男性も2023年度から2年連続で育業取得率100%を達成し、育業期間も年々長くなっています。
ー男性の育業推進に取り組み始めた背景を教えてください。
人事部長 清水 健一さん(以下、清水):社員一人ひとりがやりがいを持って活き活きと働くことを目指し、柔軟な働き方実現に向けた取組みを推進してきました。その一環として育業についても推進しています。
また、社会全体で育業を推進する流れが強まってきたことを受け、積極的に進めていくこととなりました。
安心を支える制度と温かな人のつながり
ーここから具体的な制度や取組について伺います。育業も含め育児と仕事の両立を可能とする社内制度にはどのようなものがありますか?
荒井:3歳の年度末まで育業できる育児休業制度、末子が中学3年生の年度末まで利用できる短時間勤務制度、フレックスタイム制度、子の看護休暇、育児特別休暇などの制度があります。
ー育業は3歳の年度末まで、短時間勤務制度は末子が中学3年生までと長期間利用できる制度が整っていますが、社内での利用状況はどうですか?
荒井:実際の利用状況としては、育業は2歳の年度末まで、短時間勤務制度は小学校5年生までの実績があります。
ただ、最大限まで利用せずとも、「そこまで利用できる」という制度の存在自体が、社員にとって大きな安心感につながっていると感じますね。
特に保育園への入所が難しい場合もある中、長く育業できる選択肢があることは、不安を軽減する要素に繋がっていると思います。

人事部 スペシャリスト 太田 真里子さん(以下、太田):以前は、男性が育児を理由に会社を休んだり、制度を使ったりすることが特別なことのように思われていましたが、制度の導入や利用が進む中で、今では育業が当たり前のこととして受け入れられるようになってきていますね。
ー育業期間の長期化も含め、男性の育業が増えている理由はどこにあるとお考えですか?
荒井:弊社では、産前産後の時期に1週間以内であれば有給で育業できる仕組みがあり、「1週間だけでも育業してみよう」と思えることで、育業のハードルが下がっているのだと思います。
その一歩を踏み出すと、より長い期間の育業にも前向きに取り組みやすくなるようで、実際に長期で育業する社員も増えています。
太田:また、1年間育業した男性社員に社内イベントで登壇してもらったり、育業中の社員が集まる育業懇親会の状況を社内報に掲載したりと、社内で男性の育業を“見える化”する取組も行っています。
荒井:弊社はもともと社員の年齢層が若く、以前は育業する社員が少なかったため、同じ立場で話せる仲間として、育業中の社員同士がつながれる機会をつくろうと、育業懇親会が設けられるようになりました。保育園への申請などについての情報交換や復職方法、復職後の働き方について相談できる機会として活用いただいています。
太田:こうした機会や情報に触れることで、「自分も育業してみよう」と社員が前向きに感じられるようになっていると思います。
ーかなり制度や取組が充実していますね!他にも、育業を推進する取組があれば教えてください。
荒井:管理職が本人や配偶者の妊娠・出産について申し出を受けた際、戸惑わずに育業に関する制度周知や意向確認などの必要な対応がとれるよう具体的な対応手順や必要な事務作業をまとめた管理職向けマニュアルを作成しています。
清水:社員がためらわず育業について話せるように、「申し出があったら、まずは“おめでとう”と伝え、今後の働き方について話し合いましょう」など、管理職側の声のかけ方もマニュアルに記載しています。こうした取組を通して、どの社員も安心して相談できる職場づくりを目指しています。

育業は“特別”じゃない。リアルな体験が育んだ絆と新しい日常
ーここからは、実際に育業された石川さん、西尾さんにお聞きします。
育業はどれくらいされましたか?また、育業した経緯についても教えてください。
システム統括部 グランドデザイン専管部長 石川 博志さん(以下、石川):私は3人子供がおり、1人目のときは1か月程度、その後下に双子が産まれた際は7か月間、育業しました。
子供が産まれたら育業するのが当たり前だと思っているので、育業には迷いはありませんでした。1人目のときは、少なくとも妻の体調が回復するまではと思い、1か月程度育業しましたが、次に双子の妊娠がわかった際は、もっと長く育業しなければ到底家庭が回らないと思い、早々に育業の準備をしました。

インフラソリューション部 ホストインフラグループ チーフスペシャリスト 西尾 有司さん(以下、西尾):私も2人の子供に対してそれぞれ1度ずつ、計2回育業し、どちらも1年間です。
1人目のとき1年間育業し、その際に育児の大変さを身をもって経験しました。妊娠出産はどうしても女性側に大きな負担がかかるので、育児ではなるべく妻の負担を減らしたいと思っています。そのため、2人目も1年間育業することを決めました。
ー周りの反応はいかがでしたか?
石川:社内の周りのメンバーも子育て経験者が多かったため、理解があり、快く送り出してくれました。特に双子だと話したときは、「7ヵ月で足りるの?1年くらい必要じゃないの?」と言われました(笑)。
西尾:私も、1年間という長い期間でしたが、嫌な顔をされたりすることは全くなく、上司に話した際も「いいね!」と言ってもらえました。周りのメンバーも協力的で、業務の引き継ぎもスムーズでした。
ー実際に育業し、特に大変だったことを教えてください。
西尾:育児を経験された方なら、きっと同じ思いをされたことがあると思いますが、眠れないことが大変でした。3時間おきの授乳といっても、3時間ずっと自分も眠れるというわけではないので、授乳後寝かしつけをしているうちに、また次の授乳の時間が来てしまうことも多く、心身ともに疲れました。

石川:私もやはり、眠れないのが一番つらかったですね。特に双子の場合、1人ずつ世話していると全く眠れなくなってしまうので、同時に授乳や寝かしつけをする必要がありました。せっかく寝かせても、どちらかが起きるともう1人も起きてしまいますし、さらに上の子まで目を覚ましてしまうこともあって……本当に大変でした(笑)。
大変なことはたくさんありましたが、間違いなく育業して良かったです。夫婦のどちらかが倒れたらどうしようという不安も少し軽減できましたし、初めてのハイハイや発語など、子どもの成長を間近で見られるのはやはり嬉しかったです。
ー育業したことでご自身や周りに変化はありましたか?
石川:育児の大変さは覚悟していましたし、会社としても「育業が当たり前」という雰囲気があるので、良い意味で大きな変化はありませんでした。
ただ、子供が産まれてからは仕事に割ける時間が少なくなったため、保育園の送り迎えに合わせて業務を終えられるよう、業務の効率を意識して働いています。
西尾:私も同じです。突発的な発熱などもよくあるので、常に前倒しで仕事をするようにしていますし、子供の様子を見て体調が怪しそうだと感じたら、あらかじめ周りのメンバーに早退やお休みの可能性があることを伝えています。

ー実際に利用した社内の制度や取組を教えてください。
西尾:私は育業懇親会に参加しました。育児に関する情報共有や復職に向けての相談などもできましたし、大人と話すことが久しぶりだったのでリフレッシュになりました。
石川:子の看護休暇をよく利用しています。3人子どもがいると風邪や感染症をうつし合ってしまうので、こういった休暇があるのはありがたいです。また、健康診断や予防接種に活用できる点も助かっています。
誰もが安心して、活き活きと働ける職場へ。ともに育む、これからの働き方
ーさまざまな制度を社員の方が利用していますが、育業を推進することで会社にポジティブな効果はありましたか?
荒井:育業する社員が増えたことで、育業への理解が広がり、復職時のサポートも丁寧に行き届くようになってきました。会社としても、育業を支える土台が以前より確かなものになっていると感じています。
太田:私は人事の採用も担当していますが、その際に「ライフステージが変わっても永く活き活きと働ける会社です」と自信をもって伝えられるようになりました。

ー育業の推進にあたり、今後の展望を教えてください。
清水:弊社は社員の声をもとに制度を少しずつ整えてきたことで、育業を支える仕組みが着実に充実してきたと考えています。
これからも一人ひとりの声に耳を傾けながら、制度づくりはもちろん、その運用や日々のサポートも含めて、誰もが安心して、活き活きと働ける環境を育んでいきたいです。
――ありがとうございました。
記事の内容は掲載時点の情報に基づいております。



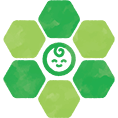






.jpg)
