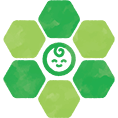掲載日:2025年11月4日
グラクソ・スミスクライン株式会社
インクルージョンを実感できる職場へ。育業を通じて見えた、支え合いが生む活躍の土壌
感染症や呼吸器疾患、がん、免疫関連疾患など、さまざまな健康課題に挑むグローバルヘルスケア企業、グラクソ・スミスクライン(GSK)。サイエンス、テクノロジー、人財を結集し、“病に先手を打つ”ことを存在意義として掲げ、医療用医薬品やワクチンの開発・提供などを行っています。社員の活力こそが企業の原動力という考えのもと、活き活きと働ける環境づくりに注力し、ライフステージに応じた柔軟な働き方を支える一環として、育業の推進にも力を入れています。
そこで、今回は、人財本部 労務部長の浅賀 伸陽(あさか のぶはる)さん、ジャパンコマーシャル&メディカルテックグループマネージャー 大塚 亜美(おおつか あみ)さん、ジェネラルメディスン本部 プライマリーケア営業 フィールドエキスパート 阿南 太亮(あなみ だいすけ)さん、実際に育業を経験されたメディカル本部 ジャパンリアルワールドエビデンス&ヘルスアウトカムズリサーチ エビデンスシンセシス&データイノベーション リード 川松 真也(かわまつ しんや)さんに、育業の取組や育業推進による社内からの声などについてお話を伺いました。

育業は特別なことではない、支え合う風土を育てる
―貴社における育業の状況について教えてください。
人財本部 労務部長 浅賀 伸陽さん(以下、浅賀):2020年時点では男性の育業取得率は4%でしたが、2024年には79%まで上昇しました。年々、着実に上がっています。
―すごい伸び率ですね!男性の育業推進に取り組み始めた背景を教えてください。
浅賀:弊社では、全社員が家庭と職場の両方で活躍できるよう、インクルージョンの風土醸成に力を入れています。男性の育業推進も、その取組のひとつです。
たとえば、制度を正しく理解し、安心して活用できるよう、今後お子さんが生まれる予定の社員や管理職を対象にセミナーや研修を実施しています。さらに管理職には、「メンバーが不在になることも見越したマネジメントが必要」という観点を伝え、互いにフォローし合える職場づくりを促しています。育業を特別なことではなく、日常のマネジメントの一部として根付かせることが、育業取得率が伸びている要因の一つなのではないかと考えています。

―今後、育業推進にあたり課題に感じている点があれば教えてください。
浅賀:職種によって 、育業取得率に差があることが課題です。そのため、計画的な育業への支援や、上司との事前調整、復職後の柔軟な働き方の設計などをサポートしています。社員が感じる育業へのハードルを下げ、より安心して育業を選択できる環境を目指して取り組んでいます。
90日間有給での育業、相談できる場など、独自の制度や取組が育業を後押し
―「育業」や「家庭と仕事の両立」を可能とする社内制度について具体的に教えてください。
浅賀:弊社では、男性育業の推進や社員がより活き活きと働ける職場環境づくりに向けて、法を上回る独自の制度を整えています。
中でも特徴的なのが、2023年4月から取り入れた「GSK育児特別有給休暇」制度です。これは、2歳未満の子どもがいる社員を対象に、90営業日分、100%有給で育業できる制度です。
また、パートナーが切迫早産になった場合など、子どもが生まれる前のトラブルや家族の体調不良時に活用できる年間20営業日まで有給の「GSK看護特別有給休暇」という制度もあり、多くの社員が活用しています。
―制度以外にも、さまざまな取組を行っていると伺いました。そちらについても詳しく教えてください。
浅賀:先ほどご紹介したセミナーや研修に加えて、2024年には両親学級も開催しました。この両親学級は、子供が生まれた後の1日のスケジュールや、育児における具体的なタスクなどを、業務時間中に学べる内容となっています。
今後育児を予定している社員だけでなく、その上司や同僚も対象にしており、参加した社員からは「勉強になった」「このような場があるのはありがたい」などの声がありました。
ジャパンコマーシャル&メディカルテックグループマネージャー 大塚 亜美さん(以下、大塚):また、私と阿南が参画する社内のWLI(ウーマンズ・リーダーシップ・イニシアチブ)でも、さまざまな支援活動を行っています。WLIとはGSKのERG(Employee Resource Group)の一つです。ERGとは、職場の多様性・公平性・包括性(Inclusion)を推進するために、共通の価値観や関心を持つ従業員が自発的に集まり活動する社内コミュニティです。自発的ですが、上司と相談の上、仕事の一環として取り組んでいます。名前に“ウーマン”とありますが、性別を問わず誰もが活躍できる環境を目指し約20人のメンバーで活動しています。

ジェネラルメディスン本部 プライマリーケア営業 フィールドエキスパート 阿南 太亮さん:プライベートの友人が少ない地域で働いている社員も多く、職場が人とつながれる唯一の場というケースもあります。しかし、育業によってその関係が一時的に途切れ、復職後の職場環境に不安を感じる社員も少なくありません。
そのような不安を解消するべく、社内のチャットツールを活用し、「育児と仕事の両立」「家事の分担」「小1の壁」など、さまざまなテーマについて話すオンラインイベントを開催しました。参加者からは「参考になった」「同じ悩みを持つ人がいることに安心した」と好評です。

大塚:他にも、ロールモデルの経験をもとに学び合う少人数制の座談会を昨年から今年にかけて10回以上開催しています。
それぞれのテーマに即した経験者と、これから同じような状況を迎える予定の社員が10人程度集まって、自由に語り合っていただいています。男性育業をテーマにした回も開催していて、リアルな悩み・体験が共有される情報交換の場になっています。
「育業」が家族や仕事との向き合い方を見つめ直すきっかけに
―ここからは、実際に育業された川松さんにお聞きします。
育業したタイミングと期間を教えてください。
メディカル本部 ジャパンリアルワールドエビデンス&ヘルスアウトカムズリサーチ エビデンスシンセシス&データイノベーション リード 川松 真也さん(以下、川松):私は子供が2人おり、1人目の時は、妻の職場復帰に合わせて、子どもが生後6~7か月の頃に2か月間、育業しました。
2人目の時は出産直後から2か月、その後1か月ずつの計3回に分け、2回目は上の子の夏休みに合わせて、3回目は再び妻が復職するタイミングで育業しています。
―育業しようと思った理由を教えてください。
川松:第1子の妊娠時、急なお休みで迷惑をかけてしまうかもしれないと思い、早めに妻の妊娠を上司へ報告しました。
すると上司から、「育業しないの?」という言葉が返ってきたんです。当時はまだ男性の育業が一般的ではなく、制度は知っていたものの、自分が育業することは想定していませんでした。育業することを前提に今後のことを考えてくれたことにびっくりしました。
そのやりとりをきっかけに、前向きに育業することを検討するようになりました。
―実際に育業した感想を教えてください。
川松:率直に、育業して良かったと感じています。
自分がなぜ働いているのかを改めて考える機会となり、育児に対しても「責任を持ってしっかり育てていこう」という気持ちが芽生えました。
もちろん、大変なこともありました。特に2人目の時は、妻の体調がなかなか安定せず、家庭を回すのに苦労しました。
また、上の子が急な環境の変化に戸惑い、「ママを取られた」と不満がたまっている様子もあったので、子供との時間を意識的に作るようにしていました。
そうした日々を通じて、家族と向き合い、対話を重ねる時間を持てたことは、非常に貴重で、大きな意味のある経験だったと感じています。

―活用して良かった制度や取組があれば教えてください。
川松:家族が増えることで、育児と仕事の両立や金銭面の不安が大きくなる中、「GSK育児特別有給休暇」は非常に心強かったです。
また、社内チャットツールの育児グループにも参加しており、情報交換を行ったり、オンラインイベントにも参加したりしています。最近では「子供の夏休みをどう乗り切るか」をテーマにした回がとても参考になりました。

―育業を通じて、ご自身や周囲に何か変化はありましたか?
川松:育業以降、子供を話題にしたコミュニケーションが自然と増えました。
「お子さん、何歳になった?」と声をかけていただいたり、「育業中はどうしていたのか教えてほしい」と相談されたりすることもあります。チャットグループで知り合った方と個人的にランチに行くなど、社内でのつながりも広がりました。
また、育業する際、上長、同僚の皆さんに引継ぎなどお願いしても嫌な顔一つされなかったのが印象に残っています。自分が育業をサポートしてもらった分、仕事を通じて会社や社会に貢献したい気持ちが一層強まりましたし、周囲に育業する同僚がいたら、今度は自分が逆の立場として積極的にサポートしたいと思うようになりました。
「お互いさま」が根づく職場へ。インクルージョンが引き出す組織の力
―育業を推進することで、会社にどのようなポジティブな効果がありましたか?
浅賀:こうした取組の成果は、必ずしも目に見える数字として表れるものではありません。ただ、育業を経験したことで「意義を感じながら働けるようになった」「会社に貢献したいという気持ちが育った」という変化を感じている社員がいるのはとても嬉しいことです。
社員一人ひとりの意識が変わることで、組織全体にも良い影響がもたらされていると信じています。
―今後の育業推進における展望を教えてください。
浅賀:今後もインクルーシブな文化を醸成していくことで、企業としての潜在的な力を引き出していきたいです。互いを支え合える「お互いさま」の関係性を築き、チームで働くことの価値に繋げていくことで、安心して働き続けられる組織を目指していきます。そして、それが長期的な業績向上にもつながっていくと思います。
――ありがとうございました。
記事の内容は掲載時点の情報に基づいております。